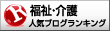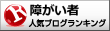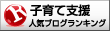長年、知的障がいのある娘の育児をしながら、
近年は・・・社会福祉法人の理事長としても活動しています。
子育てや仕事、日々の暮らしで心が疲弊し、
どうしても疲れが抜けない時期もありました。今もあります
そんな時に出会ったのが「ストイシズム」という哲学と、
そこにある「内省の習慣」の教えでした。
「旅に出て心を癒したい」けどできない現実
昔から、私は「旅に出てゆっくりして、静かに心を休めたい」
という憧れを持っていました。
日常の慌ただしさから離れ、自然の中で自分と向き合う時間は、
魂を洗うような特別な体験になると思っていました。
しかし、現実はそう簡単ではありません。
娘の世話、介護や仕事の責任、地域との関わり…
私の毎日は家族のケアに追われ、旅どころかゆっくり本を読む時間さえ
なかなか取れませんでした。
「心を休めたい」と願う一方で、体も頭も休まらず、
気持ちだけが焦って空回りすることもありました。
マルクス・アウレリウスの教えに救われた
そんな時に出会ったのが、
ローマ皇帝であり哲学者でもあったマルクス・アウレリウスの言葉です。
彼はこう言いました。
「人は好きなときに自分自身のなかに引きこもることができる。
自分の魂のなか以上に静かで揉めごとから解放される場所はない」
この言葉に「そうか、旅に行かなくても心は休めるんだ」と
気づかされました。
忙しい日々の中でも、意識して「自分の内側に引きこもる時間」をつくることが、
メンタル回復の鍵だったのです。
「内省の時間」を持つとは?
私の場合、それはジャーナリング(ノートに自分の思いを書き出すこと)や、
スマホを置いて静かに内省をする時間でした。
家事や仕事の合間、子どもたちが寝静まった後のほんの少しの時間でも、
自分の感情や考えを文字にしたり、好きな本の言葉に触れたりすることで、
心が落ち着き、エネルギーが充電されるのを感じました。
特に、子育てにおいては
「自分を責めてしまう」「できていない自分にイライラする」
ことも多いですが、
そんなときも内省の時間を取ることで「それでいいんだよ」と
自分を肯定できるようになりました。
なぜ「旅に出る」ことにこだわっていたのか
私が旅に憧れていたのは、日常の慌ただしさから
「完全に離れたい」という気持ちが強かったからです。
でも、その根底にあったのは「心の内側に静かな場所がない」
ということだったのだと思います。
日々の問題に振り回されて、
自分の心の声を聴く余裕を持てずにいたのです。
ストイシズムが教えてくれたのは、
心の静かな場所は「外」ではなく「自分の中」にあるということ。
メンタル回復は「習慣化」が大事
最初は意識して1日5分でもいいから、
自分の内側に向き合う時間を持つことを心がけました。
・スマホを置いて静かに呼吸を整える
・日記にその日の感情を書き出す
・好きな本の一節をゆっくり読む
忙しくても「これだけはやる」と決めることで、
次第に心が落ち着き、疲れが和らぎました。
この習慣ができると、慌ただしい日々の中でも自分軸がぶれにくくなり、
余計な心配やストレスから解放される好循環が生まれました。
「旅に出ること」が特別ではなくなる日
心の静かな場所を自分の内側に持てるようになると、
かつて憧れていた「旅に出て本を読む」ことが、特別なことではなくなりました。
いつでもどこでも「自分の魂に潜る」時間があるから、
たとえ家の中であっても旅のような心地よさを感じられるようになったのです。
まとめ:いますぐできるメンタル回復の習慣
-
忙しくても、1日数分でいいので「内省の時間」を持つ
-
スマホや家事から離れて、自分の心に意識を向ける
-
ジャーナリングや読書など、自分を見つめる手段を取り入れる
-
継続することで、心の静かな場所が自分の内側にできる
もし「旅に行ってリフレッシュしたい」と思っているなら、
まずはこの内省の習慣から始めてみてください。
私もこれで何度も救われました。
大切なのは、心の休まる場所を外に求めるのではなく、自分の内側に作ること。
これができれば、日々の慌ただしさも、
重い責任も、少しずつ軽くなっていくはずです。
あなたの心にも、静かな「魂の避難所」がありますように。