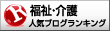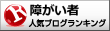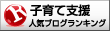こころのティーカップに水がたまる
障害のある子を育てていると、
日常のストレスや疲れが想像以上に積み重なっていきます。
療育や病院の送迎、学校とのやり取り、兄弟姉妹のケア、仕事との両立…。
一つ一つは何とかこなせても、気づかないうちに
「こころのティーカップ」に水がどんどん溜まっていきます。
そして限界が近づいたとき、ようやく「もう無理…」と感じる。
私自身も36年間、障害のある娘を育ててきて、
このカップが溢れそうになる経験を何度もしてきました。
だからこそ、あふれる前に気づくサインを知っておくことが大事なのです。
「あ、あぶない」と気づくためのサイン
心理学では、ストレスのサインは大きく三つに分けられます。
-
心理的なサイン
不安が強くなる、イライラしやすくなる。 -
行動的なサイン
集中できない、眠れない、甘いものやアルコールが増える。 -
身体的なサイン
肩こり、頭痛、動悸、血圧の上昇など。
障害児ママの世界では
「寝不足」「怒りっぽくなる」「楽しかったはずのことが楽しめない」
などが典型的なサインです。
私自身、「今日は子どもよりも私が爆発しそうだな」と感じたとき、
それはカップがいっぱいの証拠だと受け止めるようにしています。
セルフケアは“できることから”
本やネットにはいろいろなストレス対処法が書かれています。
でも大事なのは、「無理なくできる方法を、自分の生活に取り入れること」です。
-
気持ちを書き出して整理する「ジャーナリング」
-
好きな香りで深呼吸する
-
数分でも体を伸ばすストレッチ
-
「おまもりリスト」を作り、気持ちが落ちそうなときに読み返す
どれも難しいことではありません。
むしろ「これくらいならできるかも」と思えるものから始めるのが継続のコツです。
「私は今このレベルのストレスだから、この方法じゃなきゃいけない」
と思う必要はありません。
とにかく心が少し軽くなれば、それで十分なんです。
周囲にしてほしいサポート
心の限界が近いとき、家族や周囲の人からの言葉かけも大切です。
「頑張って」と言わない方がいい、という話をよく聞きます。
でも実は、心理学的には “少し動くこと” が回復につながることがわかっています。
たとえば、
-
窓を開けて新しい空気を入れる
-
ほんの数分でも散歩をする
-
台所に立ってコーヒーをいれる
こうした10%くらいの力でできる行動が、気持ちの切り替えに役立つのです。
「休みなさい」だけでは、逆に気持ちが沈んでしまうこともあります。
障害児育児の中では、心身のエネルギーが枯渇しがちです。
だからこそ「小さく動ける」工夫を支えてもらえると、とてもありがたいのです。
「心が弱い」なんて思わなくていい
昔は「心が限界になるのは弱い人」という偏見がありました。
でも、子育てにおいて心が限界になるのは、弱さではなく環境のせいです。
支援や協力が足りない環境に置かれれば、誰でも心は疲れ切ります。
「私は強いから大丈夫」と思っている人でさえ、
突然倒れてしまうこともあるのです。
だからどうか、自分を責めないでほしいのです。
心は、個人の問題ではなく、環境との相互作用によって変わるもの。
私は何万件もの相談を受ける中で、その事実を実感してきました。
体から心をゆるめる
最後にもう一つ。
心を落ち着けるのは難しいけれど、体をゆるめることは意外と簡単にできます。
呼吸法、ヨガ、ストレッチ、温かいお風呂…。
も体をほぐすことで、自然に心も落ち着いていきます。
私も「落ち着こう、落ち着こう」と頭で繰り返すより、
体を緩めることに意識を向けるほうがずっと効果的でした。
体と心はつながっています。
だからこそ、体を整えることも大切なセルフケアなのです。
まとめ
障害のある子を育てる親だからこそ、
心のティーカップがいっぱいになりやすい。
だからこそ、あふれる前に気づく力と、自分をゆるめる工夫が必要です。
-
イライラや不眠に気づいたら「サイン」と受け止める
-
セルフケアは“できること”から始める
-
周囲は「小さく動く」を支えてくれるとありがたい
-
心が弱いからではなく、環境が大きい
-
体を緩めると、心も緩んでいく
私たち親が元気でいることが、子どもの安心にもつながります。
「心のティーカップ」を守ることは、子どもを守ることでもあるのです。