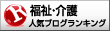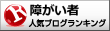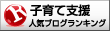「障害」児を持つ親であるということは・・・私の経験上・・・
「障害」児を持つ親であるということは・・・私の経験上・・・
多分・・人生の中で想定しえなかった・・・非常に大変なことである
って認識があります。だから・・・まずは・・・
自分の感情さえコントロールできない・・・そんな状態が続くことも・・・
致し方ないのだとも思います。
だからこそ・・・言い表すことのできない感情的な葛藤や・・・
自分自身の自己嫌悪といった感情がわき起こることは自然なことだと私は思います。
自分が子どもを愛せないと感じること・・・なんだかいなくなればいい・・・
とか・・・なんで私ばっかり・・・とか・・・
思うこと自体は悪いことでないと私は思います。私自身もそうでしたし・・・・
だから・・・精神的な負担が大きい場合・・・
プロのカウンセラーや心理療法士と話すことも有効だと私は思います。
私たちの時代は・・・なかなか巡り合うことができなかったこと
それ以前に世の中の印象が・・・精神異常・・・みたいな・・・
病院行ったら・・・出てこれない!!みたいな・・・
そんな風に思っていたから・・・(ご認識??)できなかった・・・ので
時間がかかったかもしれないし・・・
だから・・・「障害」児の子どもとの接し方や親としての役割を考る上で・・・
私がやってきてよかったこと・・・また今の時代・・・やった方がいいこと
ちょっと書いてみますね・・・
1. 自分自身を受け入れる:
自己嫌悪に陥ることは自然な感情ですが、自分を責めすぎないようにしましょう。
それぞれの親子関係はその人によって異なるものであり・・・
自分自身のやり方が・・・ってことではなく・・・
私ってここまでなんだ・・・だからどうしよう??みたいな感じで
まずは・・・受け入れることが大切です。
2. サポートを求める
子どもの「障害」に関する情報や支援を得るために・・・
地域のサポート団体や専門家に相談してみることをお勧めします。
他の親たちがどうやっているのか?どんな風にやれば楽になるのか?
なんてことも知れる機会があったり・・・交流も助けになることがあります。
(私はここで生き返ることができました・・・)
3. 自己肯定感を高める
自分の自己肯定感を高めるためには・・・
自分ができることや子どもとの良い瞬間にフォーカスして行きましょう。
人はとかく悪い部分に目が行きがちです。
自分を責めずに・・・今の自分自身をありのままに・・・認めることが大切です。
4. コミュニケーションを大切にする
子どもとじっくりコミュニケーションをとることで・・・
子どもの気持ちや必要とするものを理解しやすくなります。
(ただし・・・今そこがきついときには・・・じっくり外側に人間になって」観察してみてください)
子どもがコミュニケーションをとり辛い子もいるので・・・
だからこそ・・・言葉以外の観察も重要になります。
5. 自分の感情を整理する
自分の自己嫌悪や不安な気持ちと向き合うためには・・・
自分の感情をまずしっかり整理することが重要ではないでしょうか?
感情日記をつける・・・とにかく書き出してみて客観的に見てみる
信頼できる方のカウンセリングを受けるなど・・・
自分にあった方法で感情を処理していきましょう。
「障害」児の子どもとの関わりは・・・親子間の信頼や愛情を築く過程です。
誰もが一緒のペースではありません。
そして長く続いていくものでもあります。
だからこそ・・・
焦らず、ゆっくりと向き合い、親としての役割を楽しみながら・・・
子どもと一緒に成長していくような感覚が・・・大切なような気がします。